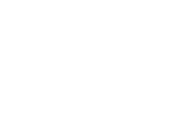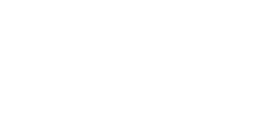実はリサイクル事業とは言わない??斎藤英次商店の「本当の事業」を説明します!
はじめに
皆さんこんにちは、斎藤英次商店マーケティングチームです。
リサイクルという言葉を聞いたことがないという方は、おそらくほとんどいないと思います。
それほどまでに現代社会には、地球環境や資源を大切にしていこうという考えが根付いているのです。
では、そんな皆さんにご質問です。
「再生資源卸売業」という言葉を聞いたこと、ありますか?
当社の事業をご説明する際に、必ず登場するこの「再生資源卸売業」、多くの人はイメージができず、どんなものか分からないのではないでしょうか?
「え?リサイクルとなにか違うの?同じでしょ?」
「そもそも再生資源ってなに?」
そんな疑問をお持ちになった方のために今回は、私たちが行っている事業の1つである「再生資源卸売業」についてご説明します!
普段あまり意識しないビジネスかもしれないですが、実は私たちの地球環境を守るために、非常に重要な役割を果たしているのです。
「再生資源」とはなにか
まず、再生資源という言葉の意味を解説していきます。
再生資源とは、使い終わったものやその副産物のうち、適切な処理をすることによって、原料などとして利用できるものを指します。具体的には、びんや缶、紙、ペットボトル、衣類などなど、皆さんが家庭のごみを分別して資源ごみとして出しているものが主になります。
再生資源が生まれかわるまで…
では、どのような流れで再生資源が利用可能なものに姿をかえていくのでしょうか?
ここでは、当社が主に扱っている「古紙」を例に、再生資源が生まれ変わるプロセスを説明していきます。
① 回収・収集・選別
まず、地域の事業者や一般家庭から排出された、段ボール、新聞、雑誌などの紙を回収します。回収された紙は種類ごとに選別します。異物や禁忌品といった、混入してはいけないものが入っていると、せっかくの資源が無駄になりすべて廃棄物となってしまうため、可能な限り取り除きます。
回収は、パッカー車という下記の写真のような車両を使って行います。

② 加工・圧縮・販売
次に、紙資源を運搬しやすいように加工します。
当社のリサイクルセンターでは、「ベーラー」と呼ばれる機械に紙資源を投入し、圧縮して運びやすい状態にします。
こうした処理を行った紙資源を、製紙会社に販売しているのです。

③ 資源→製品へ
販売した紙資源は、専用の設備で加工します。
そうすることで、紙資源は再び私たちが普段読んでいる新聞になったり、雑誌になったり、物を運ぶ段ボールになったりするのです。
どのように回収された紙資源が再び製品になるかは、下記のブログで詳しく解説しています。よろしければご覧ください。
鶴見製紙の工場見学で実感!トイレットペーパーになるまでの紙の物語
このようなプロセスを経て、市場から回収された紙は製品へと姿を変えるのです。
では皆さんは、「再生資源卸売業」が上記のどのプロセスに該当するのかわかりますか?
斎藤英次商店の再生資源卸売事業
再生資源卸売業は、市場で排出された再生資源を集め、それを次の製品を作るための原料として販売するビジネスです。
先ほど説明したプロセスでいうところの、「①回収・収集・選別」と「②加工・圧縮・販売」の部分を担っている事業になります。
一方リサイクル業は、資源を再利用して製品を製造する、プロセスでいう「③資源→製品へ」の部分を主な業務にしている事業です。
リサイクル業が、資源を製品に変え、再び利用できるようにする最終的な工程を中心に据えた事業であるのに対して、再生資源卸売業は回収・加工した資源を製品に変えるのではなく、資源を製品に変えてくれる企業に販売する事業になります。
斎藤英次商店の事業をリサイクル業ではなく、再生資源卸売業と説明しているのはこういった違いがあるからなのです。
まとめ
私たちの生活と密接に関わる「再生資源」。
それを集め、循環させ、再び利用できるようにすることが、私たち斎藤英次商店の使命です。
しかし、それを実現するためには、私たちだけではなく、多くの方々の協力があってこそだと思います。
いくら資源を使用し新しく製品に生まれ変わらせる設備を建てても、肝心の資源を集めることができなければ製品は作れません。そしてそれと同じように、いくら回収車両を用意しても、拠点を建てても、資源が分別されていなければ回収できません。
私たちの事業も、皆さんの分別も、地球規模で見れば非常に小さなものです。けれどもその小さな行動の積み重ねが、確実に地球を守ることに繋がっています。
今日も「資源を大切にしよう」という気持ちを忘れずに行動していきましょう。