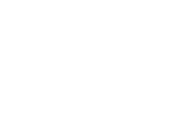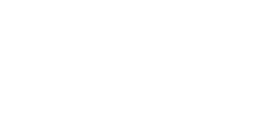段ボールの無料回収ボックスが働く人を支える ─ 斎藤英次商店がつくる地域の循環

段ボールを捨てる場所がない ─ 現場のリアルから始まった物語
1日の仕事を終え、現場をあとにする職人さんの車には、今日も資材を包んでいた段ボールが積まれています。それは仕事の成果を裏付けるように車を満たしますが、同時に小さな悩みの種にもなっています。
行政の家庭ごみ回収では、事業活動に伴って出る廃棄物は「事業系」とみなされます。多くの自治体では、事業所から出た段ボールが「事業系一般廃棄物」として扱われ、自治体や委託業者による有料回収の対象となることが多いのです。
しかし、職人さんの中には個人事業主の方も多く、現場が転々とするため、有料回収契約を結ぶにも手続きが煩雑で、現実的ではありません。
現場から戻ったあとも、段ボールを降ろし、資材を積み直す作業が待っています。仕事は終わっても、片付けという“もうひとつの仕事”が続くのです。こうした日常の負担は、多くの現場従事者にとって当たり前のように繰り返されていました。
斎藤英次商店の無料段ボール回収ボックスは、もともと地域の資源循環を支える仕組みとして各営業所に設置されていました。
これは、そこに寄せられた顧客の声が、「働く人の負担を軽くする場」としての新しい意味を与えたお話です。
現場に積み重なる「見えない負担」
かつて、ある営業所に段ボールを満載したハイエースが入ってきました。目的は無料回収ボックス。運転していたのは、地域の内装業の職人さんでした。作業後に出た段ボールは現場に残せず、毎回自宅まで持ち帰るしかなかったそうです。
「ハイエースは資材を積む倉庫代わり。不要な段ボールを載せる想定じゃないんです」と彼は話してくれました。
数日の作業で出る量は想像以上で、気づけばガレージの一角が段ボールで埋まってしまいます。行政に回収を頼む方法もありますが、事業系廃棄物として扱われるため、有料での処理が必要になります。個人事業主にとって、その費用も手続きも負担が大きいのが実情です。
だからといって、燃えるごみで出すわけにもいかず、行き場のない資源が現場の片隅で静かに積み上がっていきます。
無料回収ボックスを知った日 ─ 小さな行動が生んだ変化
ある日、別の現場で出会った電設工事業の仲間が「この近くに無料で段ボールを回収してくれるボックスがある」と職人さんに教えてくれたそうです。それが、斎藤英次商店の営業所にある「古紙回収ボックス」でした。
24時間365日、誰でも無料で持ち込めるこの仕組みが、職人さんたちの働き方を少しずつ変えていきました。
仕事を終えたあと、現場から自宅へ戻る途中に立ち寄る。積み込んでいた段ボールを次々と投入し、車内が軽くなる。
以来、現場帰りに回収ボックスへ立ち寄ることが日課になる人も増えました。
“仕事のあとに気軽に寄れる場所”があるだけで、日々の小さなストレスが確実に減っていったのです。
この出来事は一例にすぎませんが、同じような課題を抱えていた多くの職人さんの共感を呼び、口コミで「便利な回収ボックスがあるらしい」という噂が広がっていきました。

企業が“困りごと”を見逃さなかった瞬間
こうした利用者の声は、斎藤英次商店の社員の耳にも届いていました。
当時、営業所では回収ボックスの利用傾向を調べており、個人家庭よりも明らかに「事業者の利用」が増えていることに気づいていたのです。その背景には、現場ごとに発生する小規模な廃棄物処理の課題がありました。
作業現場が点在し、契約回収が難しい業種ほど、段ボール無料回収ボックスの存在価値は大きくなっていました。
「それなら、もっと多くの職人さんに知ってもらおう」とマーケティング担当者は考えました。
地域の内装・リフォーム業者の名簿を調べ、「現場帰りに、無料で段ボールを持ち込める場所があります」というダイレクトメールを送付しました。
その取り組みは反響を呼び、やがて水道・配管・空調・電設といった業種にも広がりました。
企業の広報活動というよりも、「現場の声に応える」という姿勢そのものが信頼を生んでいったのです。
▶ この段ボールはボックスに入れないで!
小さなボックスから生まれる大きな循環
職人さんたちの利用が増えるにつれて、営業所での段ボール回収量も目に見えて上がっていきました。
それは「不要物が資源に変わる流れ」が確実に広がっている証拠でした。
ボックスに集まった段ボールは営業所で分別・圧縮され、製紙会社へと出荷されます。やがて新しい段ボールとして再び社会に戻っていきます。
現場で生まれた資源が、また別の現場を支える。その循環の起点が、斎藤英次商店の営業所の一角に置かれた段ボール無料回収ボックスなのです。
利用者の多くが口をそろえて言うのは、「近くにあって助かる」という言葉です。それは利便性だけでなく、心理的な安心感をもたらしています。
ボックスが地域での信頼の象徴になっていきました。
1946年創業の斎藤英次商店は、古紙リサイクルを通して人と地域の暮らしを支える循環の仕組みを守ってきました。
無料回収ボックスの設置もサーキュラーエコノミー推進の一助となっています。
「廃棄」を「再資源化」へ変える。
「処分」を「貢献」に変える。
その積み重ねが、カーボンニュートラル社会の実現につながっていきます。

働く人を軽く、地域を軽く、地球を軽く
現在、斎藤英次商店は千葉県・茨城県に複数の営業所を展開しています。それぞれの営業所には、一般利用者も事業者も自由に使える無料段ボール回収ボックスが設置されています。
Googleマップで「近くの段ボール回収」や「段ボール 無料回収 近く」などと検索すると、斎藤英次商店のリサイクルステーションが表示されます。
「近くで、すぐに、無料で出せる」そのシンプルな安心感が利用者の信頼を支えています。
段ボール1kgを再資源化することで、おおよそ0.5〜1.0kgのCO₂排出を抑制できるといわれています。
仕事帰りに10kgの段ボールを回収ボックスに持ち込むだけで、数kg分のCO₂削減につながる計算です。
しかし、この活動の価値は数字だけでは語れません。
「現場でのストレスが減った」「帰宅後の時間が増えた」という声が広がり、それが結果として持続可能な働き方と暮らしを後押ししています。
斎藤英次商店の回収ボックスは、段ボールを“減らす”装置ではなく、人の負担を軽くし、地域と地球を軽くする装置でもあるのです。
捨てるから、つなぐへ ─ 循環の起点としての回収ボックス
夜の回収ボックスに、段ボールを入れる音が響きます。それは仕事の終わりを告げる音であり、同時に新しい循環の始まりを知らせる音でもあります。
斎藤英次商店の無料段ボール回収ボックスは、単なる「ごみ箱」ではありません。それは地域の誰かを支える小さな拠点であり、働く人・地域・地球をつなぐ循環のハブです。
明日もまた、誰かが回収ボックスに段ボールを託します。
そしてそれは、新しい紙として再び社会へ戻り、また誰かの仕事を支えていきます。
VISION2046
Zero Waste 廃棄物のない社会を目指して
私たちは、世界規模の資源循環をにないます。
そのために、誰でも簡単に楽しくリサイクルできるようにします。
Zero Carbon 温室効果ガスを排出しない社会を目指して
私たちは、脱炭素型の資源循環ビジネスモデルを創造します。
そのために、デジタル技術や再生可能エネルギーを活用します。