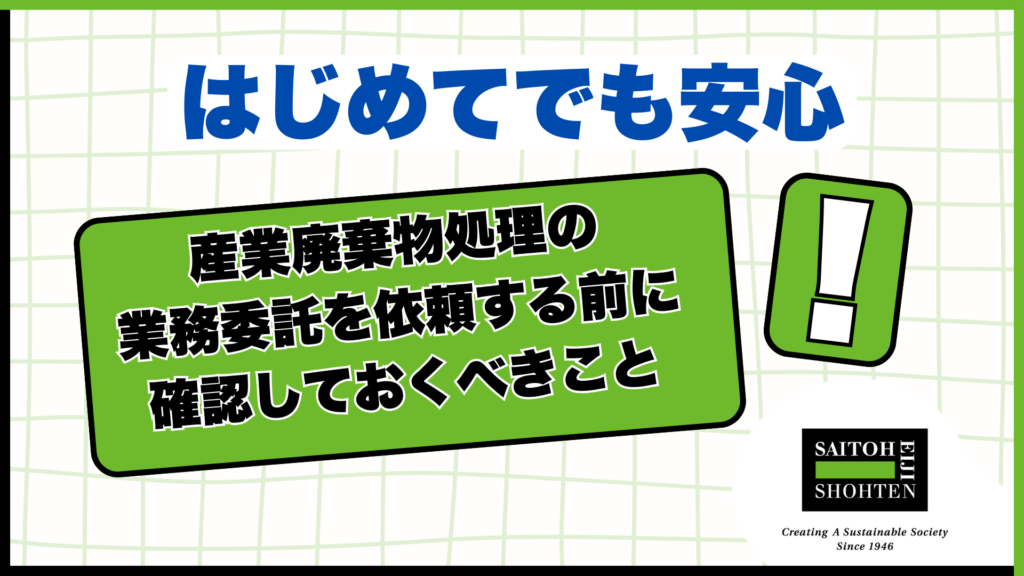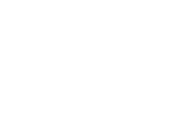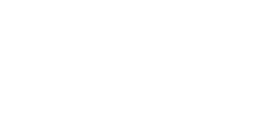はじめてでも安心!産業廃棄物処理を依頼する際に知っておくべきことを解説!!
はじめに
「廃棄物の処理の依頼って難しそう…」
「はじめて対応するけど、何から学べばいい?」
「マニフェストとか委託契約ってどういうもの?」
この記事では、このようなお悩みを持つ自社事業に伴って発生した産業廃棄物の処理をはじめて行う方向けに、基礎から丁寧に解説します。
さらに、業者に依頼するときに必ず必要になる「委託契約」や、自社の廃棄物が適切に処理されたか確認・証明するうえで欠かせない「マニフェスト制度」についても詳しくご紹介します。
また、本記事下部に産業廃棄物のご依頼に必要な準備や、委託契約・マニフェスト制度について、図を交えて解説した「お役立ち資料」もございますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 産業廃棄物とは?
実は事業活動から出るごみが、すべて産業廃棄物になるわけではありません。
まず、廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
工場や建設現場などの事業活動に伴い発生する廃プラスチック類、汚泥、廃油など、法律で20種類に指定されているものが「産業廃棄物」です。
これらは排出事業者が処理責任を負い、委託契約やマニフェスト制度に基づいて適正に処理する必要があります。
一方で、一般廃棄物は主に家庭ごみや、企業の事業活動に伴って発生する、法律で指定された20種類以外の廃棄物(一般事業系廃棄物)のことです。
これらは、市区町村が定めるルールに従って排出する必要があります。
廃棄物の区分
- 産業廃棄物: 工場や建設現場などで発生するごみ(廃プラスチック類、汚泥、廃油など20種類)。排出事業者が処理責任を負う。
- 一般廃棄物: 家庭ごみ(生ごみ・家庭の紙くずなど)と事業に伴ってでた、産業廃棄物以外のごみ(一般事業系廃棄物)。市区町村が収集・処理
2. 産廃処理の基本的な流れ
産廃処理は単に「ごみを捨てる」ことではなく、法律に基づいた手順で行う必要があります。以下は一般的な流れです。
産業廃棄物処理の流れ
分別: 廃プラスチック類、汚泥、廃油、金属くずなど種類ごとに仕分け。
↓
保管: 飛散や流出を防ぐ。表示(品目・排出事業者名など)も必要。
↓
収集運搬: 許可を持つ業者に委託。
↓
中間処理: 焼却・破砕・圧縮・リサイクルなど。
↓
最終処分: 埋立処分や再資源化。
この流れをきちんと守ることで、環境保全と法令遵守が両立します。
3. 産業廃棄物の代表的な種類と具体例
ここでは、初心者の方がよく耳にする代表的な産廃の種類を具体例付きで紹介します。
| 種類 | 概要・処理方法 |
|---|---|
| 燃え殻 | 焼却後の灰。セメント原料として再利用される場合も。 |
| 汚泥 | 排水処理で発生する泥。脱水や安定化処理が必要。 |
| 廃油 | 機械油や食用油。再生燃料として利用されることもある。 |
| 廃酸・廃アルカリ | 化学工場や洗浄工程で発生する酸性・アルカリ性廃液。中和処理が必須。 |
| 廃プラスチック類 | 包装材や発泡スチロール、部品など。リサイクル技術が進展。 |
| 紙くず・木くず | 梱包材や建設現場の端材。再資源化しやすい。 |
| 金属くず | 鉄、銅、アルミなど。スクラップとして高い価値。 |
| ガラス・陶磁器くず | 破片や製造不良品。破砕・原料化して再利用。 |
| 繊維くず | 布や繊維片。燃料や再生繊維に利用可能。 |
| 石綿含有廃棄物 | アスベスト入り建材。専門業者による厳格な処理が必要。 |
これらの品目分類は、排出事業者自身で分類の判断をしたうえで、依頼する業者を探すことが理想的です。
しかし、廃棄物によってはさまざまな品目を含む「混合廃棄物」などもあり、自身で判断するのが難しい場合も多々あります。
まずは業者等に問い合わせて、現地調査等を行ってもらうのがオススメです。
4. 産業廃棄物処理における委託契約の基本
次に重要なのが産業廃棄物の処理に関する委託契約です。
処理を依頼するときに「誰が、どんな廃棄物を、どの範囲で、どのように処理するか」を書面で定めることです。
- 対象となる廃棄物の種類
- 委託範囲(収集運搬/中間処理/最終処分)
- 処理方法
- 契約期間
- 責任分担
5.マニフェスト制度の概要
産業廃棄物の処理に「マニフェスト」が必要なのは知っている…という方は多くいますが、内容は意外と分からない方も多くいるのが現状です。
マニフェスト制度は、廃棄物の排出から最終処分までの流れを記録・確認できるようにすることが目的の仕組みです。
これにより不法投棄を防ぎ、排出事業者が最後まで責任を持つことを証明します。
📄 紙マニフェスト
-
-
- 形式: 6枚綴りの複写式伝票を使用
- 流れ: 排出事業者 → 運搬業者 → 処理業者と順に伝票を渡し、最終的に返送されて完了
- メリット: 導入しやすい、システム不要、従来からの運用で慣れている業者が多い
- デメリット: 記入ミスや紛失リスク、返送漏れが起きやすい、保管スペースが必要
- 保存義務: 5年間の保存が必須(紙のままファイル管理)
-
💻 電子マニフェスト
-
-
- 形式: 専用のクラウドシステム(JWNETなど)を利用
- 流れ: データをオンラインで入力・共有し、処理完了もシステム上で確認
- メリット: 記入・返送ミスが減少、保存・検索が容易、報告業務を効率化できる
- デメリット: インターネット環境が必要、システム操作に慣れるまで時間がかかる
- 保存義務: システム上に自動保存されるため管理が容易
-
⚖️ どちらを選ぶべき?
小規模事業所やスポット的な排出のみなら紙マニフェストでも十分対応可能です。
一方で、廃棄物の種類や量が多い企業、支店や現場が複数ある企業は、電子マニフェストを導入することで管理の効率化・法令遵守リスクの低減が期待できます。
特に最近では国や自治体も電子化を推奨しており、将来的には電子マニフェストが主流になると予想されています。
6.よくある質問(Q&A)
Q1. はじめて産業廃棄物処理をする場合、まず何をすべき?
A. 出る廃棄物の種類を把握 → 許可業者に相談 → 委託契約を結ぶ → マニフェスト運用開始。この順番が基本です。
Q2. マニフェスト制度は必ず使うの?
A. はい。産廃処理では原則必須です。紙・電子どちらかで交付・保存しましょう。
Q3. 委託契約は口頭でもいい?
A. いいえ。必ず書面(紙・電子契約)で交わす必要があります。
Q4. 委託契約とマニフェスト、どちらが重要?
A. 両方とも欠かせません。委託契約で事前に委託処理の約束を定め、マニフェストでその約束の実行・確認をするためです。
7. 産業廃棄物処理をスムーズに行うには?
✅ まとめ
- 産廃処理は排出事業者の責任で行う。
- 処理の流れは「分別 → 保管 → 運搬 → 中間処理 → 最終処分」。
- 委託契約で業者とのルールを明確に。
- マニフェスト制度で処理の流れを記録し、不法投棄を防ぐ。
今回はじめて産業廃棄物の処理を依頼する方は、これらのポイントを押さえて業者選定をしましょう。
基本的な知識があるだけで、依頼から収集・運搬・処理までのスピード感はグッと上がります。
8. より詳細な「お役立ち資料」はこちら
産業廃棄物処理を進めるうえで欠かせない委託契約やマニフェスト制度について、さらに詳しく知りたい方のために、「お役立ち資料」をご用意しました。
図やフローチャートを交えて解説しているので、初めての方でもスムーズに理解できます。
ぜひダウンロードして実務にお役立てください。